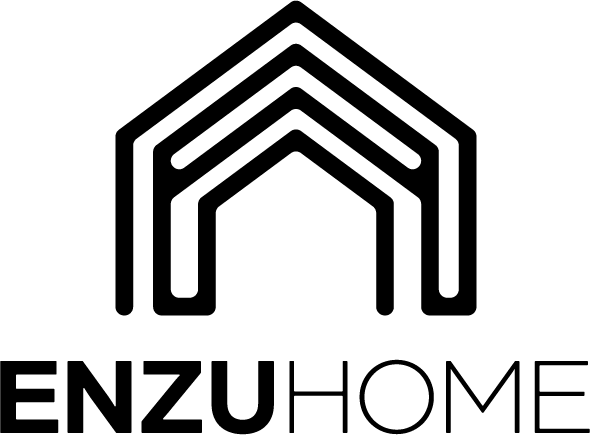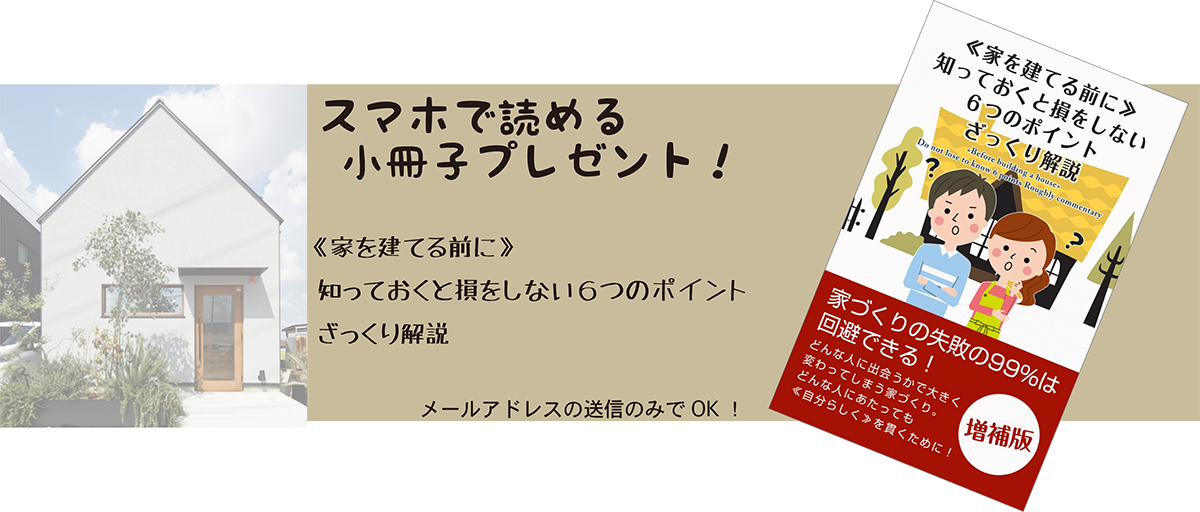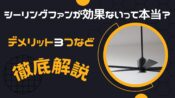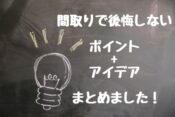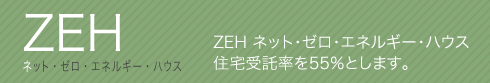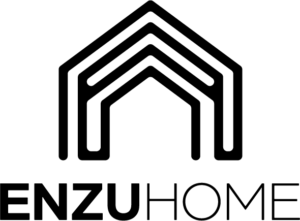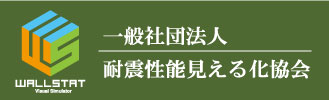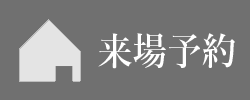【知らないと後悔】「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違いやデメリット5つを解説!

- 耐震等級3相当の評価ってどうなの?
- メリット・デメリットを知りたい
- 耐震等級3相当の家は将来的に売却しやすい?
マイホームを建てる際、耐震性能を重視する方は多いですよね。
特に「耐震等級3相当」という言葉を聞いたことがあるけれど、「本当に安全なの?」「耐震等級3とは何が違うの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで、住宅業界のプロが耐震等級3相当について、あなたの疑問を解決します。
- 耐震等級3と耐震等級3相当の違い
- 耐震等級3相当のメリット・デメリット
- よくある疑問とその答え
あなたが耐震等級3相当の本当の価値を理解することで、家づくりの判断材料になりますよ。
特に、これからマイホームを建てる予定の方は、ぜひ最後までご覧ください。
結論:耐震等級3相当とは「耐震等級3の耐久性があるも認定機関へ申請していない住宅」
この記事のもくじ

【世界一分かりやすい「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違い】*読まないと騙されます
— 現場death【木造注文住宅の情報発信】 (@KantokuDeath) March 8, 2025
「耐震等級3」と「耐震等級3相当」は、一見よく似ているようで、じつは大きな違いがあります。「耐震等級3」は国や公的なルールに沿った審査を受けて、「この建物は一番高い耐震性能を持っていますよ」と…
耐震等級3相当とは、建築基準法の耐震基準を満たし、設計上は耐震等級3と同等の耐震性能を持ちながらも、公的な認定を取得していない住宅を指します。
耐震等級とは、建物の耐震性能を示す指標で、以下の3つのランクに分類されます。
| 耐震等級 | 耐震性能の基準 |
|---|---|
| 耐震等級1 | 建築基準法の最低基準を満たし、震度6強~7の地震で倒壊しないレベル |
| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の耐震性能(避難所や病院などの基準) |
| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の耐震性能(警察署や消防署と同等) |
- 耐震等級3と同等の耐震性を持つが、公的な認定を受けていない
- 申請費用や手続きが不要なため、コストを抑えられる
- 地震保険の割引や住宅ローンの優遇を受けられない可能性がある
- 第三者機関の証明がないため、実際の耐震性を確認しづらい

つまり、耐震等級3相当の住宅は、費用を抑えつつ高い耐震性を確保したい人には適していますが、公的な認定がないことで金銭的なメリットを受けられないリスクがある点も理解しておく必要があります。
関連記事:耐震等級にもいろいろある?
「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違い5つ
耐震等級3と耐震等級3相当は、一見すると同じように思えますが、いくつかの重要な違いがあります。
耐震性の高さはどちらも同等とされますが、公的な認定の有無や住宅ローン・地震保険への影響など、長期的な視点で見ると違いが明確になります。
ここでは、耐震等級3と耐震等級3相当の5つの違いについて詳しく解説します。
違い①:公的な認定の有無

耐震等級3は、国や自治体が認定する公的な基準を満たした住宅であり、第三者機関による審査を通過しています。
一方、耐震等級3相当は、設計上は耐震等級3と同等の耐震性を持っているものの、公的な認定は受けていません。
| 項目 | 耐震等級3 | 耐震等級3相当 |
|---|---|---|
| 認定機関による審査 | あり | なし |
| 耐震性能の証明 | 公的に証明される | 設計者の判断による |
違い②:地震保険の割引の適用可否
「耐震等級3」の家なら、地震保険が50%割引になります。
— 地盤災害ドクター横山芳春@住宅の災害リスクの専門家 (@jibansaigai) January 23, 2025
盲点は、第三者評価機関の認定を受けていない「耐震等級3相当」では、この割引対象にならないことです。
「耐震等級3で割引を受けるつもりだったのに、実際には耐震等級3相当で受けられない」、ということがないようにご注意下さい。 https://t.co/m7qyiIImWh pic.twitter.com/ZShu1nybZ4
耐震等級3を取得した住宅は、地震保険の割引を受けることができます。
耐震等級が高いほど割引率も上がるため、耐震等級3の住宅は最大50%の割引が適用されます。
耐震等級3相当の住宅は、公的な認定がないため、耐震等級による地震保険の割引は適用されません。
| 耐震等級 | 地震保険の割引率 |
|---|---|
| 耐震等級1 | 10% |
| 耐震等級2 | 30% |
| 耐震等級3 | 50% |
| 耐震等級3相当 | なし |
違い③:住宅ローンの優遇措置の有無
耐震等級3相当の話で思い出したのだけど、
— ぐり高原 (@YHwdqo8co38N1eQ) June 28, 2023
もうあと半年で2024年ですので、断熱性能等級を
★住宅性能表示制度等により公的に証明★しなければ、住宅ローン控除が受けられなくなるので注意してくださいね。
今後は「断熱等級7相当」とか通用しませんのでご注意を。
お金ばっかりかかりますねェ。 pic.twitter.com/b3woOA3vF1
住宅ローンの中には、耐震性の高い住宅に対して金利を引き下げるフラット35S(Aプラン)などの優遇措置があります。
耐震等級3の住宅は、こうした金利優遇の対象になりますが、耐震等級3相当の住宅は認定を受けていないため、優遇を受けられない可能性があります。
| 項目 | 耐震等級3 | 耐震等級3相当 |
|---|---|---|
| フラット35Sの適用 | 可能(Aプラン対象) | 不可 |
| 金利の引き下げ | あり(10年間0.25%引き下げ) | なし |
違い④:耐震性能の証明ができるかどうか
耐震等級3相当をうたってるからって
— ぺれ🏠R4.10月末引渡済🌟 (@myhomestepfam1) September 28, 2022
3ではないから2なのかなと思いきや、照明?がなければ2ですらないんだね👀
そして証明するにはお金がかかりすぎてヤバ🙀
住宅性能証明書は申請してるけどそれで耐震等級3だったら火災保険通るのかな?
意味わからんすぎてハゲる🧑🦲
証明するのに色々お金かかりすぎ💴
耐震等級3の住宅は、第三者機関の審査を通過しているため、書類として耐震性能の証明が可能です。
一方、耐震等級3相当の住宅は、建築会社や設計士が「耐震等級3と同等」と説明するのみであり、客観的に証明する手段がありません。

そのため、将来的に売却を考える場合や、住宅の資産価値を評価する際に証明書の有無が影響する可能性があります。
違い⑤:資産価値への影響

耐震等級3の住宅は、公的に認定された耐震性能を持っているため、売却時にも資産価値が維持されやすい傾向があります。
一方で、耐震等級3相当の住宅は、第三者機関による証明がないため、買い手によっては評価が低くなる可能性があります。
| 項目 | 耐震等級3 | 耐震等級3相当 |
|---|---|---|
| 資産価値の維持 | しやすい | 低く評価される可能性あり |
| 将来的な売却 | 証明書があるため有利 | 証明ができず不利になる場合あり |
このように、耐震等級3と耐震等級3相当には明確な違いがあります。

特に、住宅ローンの優遇や地震保険の割引、資産価値の維持といった長期的なメリットを考えると、公的な認定を受けた耐震等級3の取得を検討する価値は高いでしょう。
耐震等級3相当のメリット2選

耐震等級3相当の住宅には、公的な認定がないというデメリットはあるものの、コストを抑えながら耐震性能の高い家を建てられるというメリットがあります。
また、申請の手間がない分、設計の自由度が高いことも魅力です。
ここでは、耐震等級3相当の2つの大きなメリットについて解説します。
メリット①:安く高めの耐震性能の家を建てられる
2:コストパフォーマンスの向上
— 住まいの発見館 (@hakkenkan__) February 2, 2024
耐震等級3相当の住宅は、コストを抑えつつも高い耐震性を実現しています。
申請手数料などの節約に加え、住宅ローンの金利引き下げも可能です。
これにより、高い安全性を持ちながらも経済的な負担を軽減できます。
耐震等級3の認定を取得するには、第三者機関での審査が必要になり、申請費用や構造計算費用として10〜30万円程度のコストが発生します。
また、審査基準を満たすために、より厳密な設計や追加の補強工事が必要になる場合もあります。
耐震等級3相当であれば、審査や申請にかかる費用をカットできるため、コストを抑えて耐震性能の高い家を建てられるというメリットがあります。
耐震等級3取得にかかる費用の比較
| 項目 | 耐震等級3 | 耐震等級3相当 |
|---|---|---|
| 申請・審査費用 | 10〜30万円 | なし |
| 追加の補強工事 | 必要な場合あり | 基本的に不要 |
| トータルコスト | 高め | 安く抑えられる |

特に予算が限られている場合、耐震性能を確保しながらも、トータルコストを抑えられる耐震等級3相当は魅力的です。
メリット②:設計の自由度が高い

耐震等級3の認定を取得する場合、認定機関の基準を満たすために壁の配置や建物のバランスに制約がかかることがあります。
例えば、以下のような制約が発生するケースがあります。
- 開放的な間取りが作りにくい(耐力壁を増やす必要があるため)
- 大きな窓や吹き抜けの設計が制限される
- 耐震性確保のためにデザインの変更が必要になる
耐震等級3相当の場合、公的な認定を受けないため、こうした設計上の制約が少なく、自由度の高い間取りが可能になります。
耐震等級3と耐震等級3相当の設計の自由度比較
| 項目 | 耐震等級3 | 耐震等級3相当 |
|---|---|---|
| 吹き抜けの設計 | 制約あり | 自由度が高い |
| 大きな窓の設置 | 制限される場合あり | 比較的自由 |
| 間取りの変更 | 壁の配置に制約あり | 変更しやすい |

「デザイン性を重視したい」「開放的な間取りにしたい」と考えている方にとっては、耐震等級3相当の方が理想の家を実現しやすいといえます。
耐震等級3相当のデメリット5選

耐震等級3相当にはコスト面や設計の自由度といったメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
ここでは、特に注意すべき5つのデメリットについて詳しく解説します。
デメリット①:本当に耐震等級3を取得できるか確認が不可能
耐震等級3取得してますよ
— 家づくりで失敗する人をなくしたい建築士🍀佐藤百世 (@yothubadesign) January 14, 2024
ってはっきり言わない工務店は
たいてい耐震等級3レベルに達してないです。
ちゃんとやってたら
「耐震等級3相当の丈夫な家ですよ」
なんてあいまいな言い方しないです。
耐震等級3を正式に取得するためには、第三者機関による審査と適合証明書の発行が必要です。
しかし、耐震等級3相当の場合は、審査を受けていないため、本当に耐震等級3の基準を満たしているのかを証明することができません。
特に以下の点が不透明になります。
- 設計ミスや計算ミスがあっても気づけない
- 第三者のチェックが入らないため、耐震性の確保が保証されない

「耐震等級3相当」と言われても、建築会社が独自に「相当」と判断しているだけのケースもあるため、注意が必要です。
デメリット②:金利の優遇措置を受けられない可能性が高い
これはマジなんですが、耐震等級3『相当』だと、地震保険料の割引・住宅ローンの金利優遇が受けられません🙅♀️
— ミホミホ@YouTuber&Vlogger (@mihomiho2024) December 15, 2024
公的な認定を受けていないからです🤔
デメリットとして、耐震等級3『相当』より耐震等級3の方が、建築費用自体は20~40万程度高くなります🤔
あなたなら、どちらを選びますか? pic.twitter.com/8DCUhxBDRA
住宅ローンを利用する際、「フラット35S」などの金利優遇を受けられるケースがあります。
しかし、耐震等級3相当では、正式な認定がないため、優遇措置を受けられない可能性が高くなります。
例えば、「フラット35S」の金利優遇を受けた場合と受けられなかった場合の比較は以下の通りです。
| 項目 | 耐震等級3(認定あり) | 耐震等級3相当(認定なし) |
|---|---|---|
| 金利優遇 | 0.25%引き下げ | なし |
| 総返済額の差(借入額3,000万円、35年ローン) | 約70万円の節約 | 優遇なし |

長期間にわたる住宅ローンでは、少しの金利差が総返済額に大きく影響するため、注意が必要です。
デメリット③:地震保険の割引を受けられない可能性が高い

耐震等級3の認定を取得すると、地震保険の保険料が最大50%割引されます。
しかし、耐震等級3相当の場合は、正式な認定がないため、割引の適用を受けることができません。
| 耐震等級 | 地震保険の割引率 |
|---|---|
| 耐震等級1 | 10%割引 |
| 耐震等級2 | 30%割引 |
| 耐震等級3 | 50%割引 |
| 耐震等級3相当 | 割引なし |

10年、20年と長く住むことを考えると、地震保険料の差額が数十万円以上になる可能性があります。
関連記事:耐震等級 大切にしたい命
デメリット④:住宅ローン審査に影響する可能性がある
築17年
— 身の丈LIFESTYLE (@Minotake_LS) February 15, 2023
耐震等級1相当・断熱等級4相当
まさに我が家のこと
省エネでロングローンも繰り上げられる!
普通に耐震等級3と断熱等級7は素晴らしい!と思います。耐震断熱は壊れないから最優先!
と今となっては思う。マウント取られてツライが愛着あるし大事にリフォームしていきたい。
住宅ローン審査では、物件の資産価値や安全性が考慮されます。
耐震等級3相当の家は、耐震等級3と同等の耐震性があるとされますが、正式な認定がないため、金融機関によっては住宅ローン審査で不利になる可能性があります。
例えば、以下のような影響が考えられます。
- フラット35などのローン商品が利用できない
- ローン審査で評価が下がる可能性がある
- 融資額が希望より低くなる場合がある

特に、住宅ローンの借入額を最大限確保したい人にとっては、耐震等級3を取得する方が安心です。
デメリット⑤:将来的なリフォームや売却時に評価されにくい

将来的にリフォームを検討したり、家を売却する際に、耐震性能が公的に証明されているかどうかが評価に影響します。
- 耐震等級3の認定があれば、中古住宅としての資産価値が高まり、売却しやすい
- リフォーム時に耐震補強の必要がないことが証明できるため、工事費用を抑えられる

一方で、耐震等級3相当では、買い手が耐震性能を信用しにくく、売却価格が下がる可能性があります。
耐震等級3相当に関するよくある質問5選

耐震等級3相当については、「本当に安全なの?」「後悔しない?」といった疑問を持つ方が多いです。
ここでは、よくある5つの質問にわかりやすく回答します。
質問①:耐震等級3相当は嘘なの?

耐震等級3相当が嘘というわけではありません。
ただし、正式な耐震等級3とは異なり、第三者機関による認定を受けていないため、本当に耐震等級3レベルの耐震性があるか証明できないのが問題です。
ポイントは以下の通りです。
- 耐震等級3相当=建築会社が独自に「耐震等級3相当の強度」と判断しているだけ
- 正式な審査を受けていないため、設計ミスや計算ミスがあっても気づけない可能性
- 耐震等級3を取得するには、住宅性能評価機関の審査が必須

つまり、耐震等級3相当の住宅は、施工会社の実力に大きく依存するため、信頼できる会社を選ぶことが重要です。
質問②:耐震等級3が意味ないって本当?
ポストに入ってた広告
— tetsu (@ksgNiZoMk2D09Va) February 23, 2024
「耐震等級3相当」とかほんまに書くんや…
騙される人が要ると思うと胸が痛くなる pic.twitter.com/l2jIPbDecB
耐震等級3が意味ないというのは誤解です。
耐震等級3の住宅は、震度6強〜7の地震の1.5倍の揺れにも耐えられる設計になっており、繰り返しの地震でも倒壊リスクを低減できます。
実際、熊本地震(2016年)では、耐震等級3の住宅だけが倒壊を免れたというデータもあります。
また、耐震等級3の取得には以下のようなメリットがあります。
- 住宅ローン(金利優遇)が受けやすい
- 地震保険の割引(最大50%)が適用される
- 将来の売却時に評価されやすい

耐震等級3を取得することで、長期的な安全性・経済的メリットが得られるため、「意味がない」とは言えません。
質問③:耐震等級3は後悔する?
耐震等級3の設計にはしたけれども、あとから免震にしておけば家財とかも守れたのになと少し後悔している…
— 杉並-コリ㌧@娘1歳 (@koriton77) April 6, 2023
耐震等級3を取得して後悔するケースはほとんどありません。
ただし、以下のような点を事前に確認しておかないと、後悔につながる可能性があります。
- コストが高くなる
- 耐震等級3を取得するための設計費用や審査費用が10〜30万円ほどかかる
- 間取りやデザインに制約が出ることがある
- 耐震等級3の基準を満たすために、柱や壁の配置が制限される場合がある
- 「耐震等級3相当」と混同して契約してしまう
- 「相当」ではなく、正式な耐震等級3を取得するか確認が必要

これらを事前に理解し、しっかりとした施工会社を選べば、耐震等級3を取得して後悔する可能性は低いです。
質問④:耐震等級3相当でも地震は大丈夫?

耐震等級3相当でも、適切に施工されていれば地震に強い可能性はあります。
ただし、実際に耐震等級3の基準を満たしているかは確認できません。
ポイントは以下の通りです。
- 耐震等級3相当の強度は施工会社の判断次第
- 第三者機関による確認がないため、計算ミスや手抜き工事のリスクがある
- 繰り返しの地震に対する耐久性は、正式な耐震等級3の方が安心

また、耐震等級3の認定がないと住宅ローンの優遇や地震保険の割引を受けられない可能性が高いため、費用対効果をよく考えることが重要です。
質問⑤:耐震等級3相当で長期優良住宅の認定は受けられる?
ほんとに差がありすぎですよね。これを理解するのは大変だと思います😔
— 家づくりで失敗する人をなくしたい建築士🍀佐藤百世 (@yothubadesign) May 25, 2023
長期優良住宅は耐震等級の審査をしているので「相当」ではないです。
昨年10月1日以降は耐震等級3です。
それ以前は耐震等級2でも長期優良住宅はとれました。計算方法は、品確法の計算でも許容応力度計算でもどちらも可です。
耐震等級3相当では、長期優良住宅の認定を受けられないです。
長期優良住宅の認定基準では、耐震等級2以上が必須とされており、耐震等級3を取得すればより有利になります。
しかし、耐震等級3相当では、正式な認定がないため、基準を満たしているか証明できません。
| 項目 | 耐震等級3 | 耐震等級3相当 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅の認定 | 取得しやすい | 取得できない可能性が高い |
| 税制優遇 | 受けられる | 受けられない可能性がある |
| 住宅ローン控除 | 受けられる | 条件次第 |

長期優良住宅の認定を受けることで、固定資産税の減額や住宅ローン控除などの優遇措置が受けられるため、正式に耐震等級3を取得する方がメリットは大きいです。
まとめ:耐震等級3の取得で夢のマイホームを

- 耐震等級3相当は、正式な認定がないため耐震性能の証明が困難。
- 地震保険や住宅ローンの優遇を受けるには、耐震等級3の取得が必要。
- 長期的な安心と資産価値を考え、確実な耐震性能の住宅を選択。
耐震等級3相当と耐震等級3の違いを理解し、どちらを選ぶか慎重に判断することが大切です。
特に、日本は地震が多い国であり、大規模な地震が発生するリスクを考えると、正式な耐震等級3を取得するメリットは非常に大きいといえます。
- 第三者機関による認定があるため、確実に耐震性が証明される
- 住宅ローンの金利優遇や地震保険の割引(最大50%)が受けられる
- 長期優良住宅の認定を受けやすく、税制優遇も適用される
- 将来的な売却時にも資産価値が評価されやすい
一方で、耐震等級3相当は費用を抑えられるメリットがありますが、本当に耐震等級3の性能があるのか証明できないため、不安が残るというデメリットもあります。
後悔しないために、以下の点を確認しましょう。
- 契約前に「耐震等級3の認定を取得するのか」「相当なのか」を明確にする
- 施工会社の実績や信頼性を確認し、構造計算の内容をチェックする
- 長期的な安心と経済的メリットを考慮し、耐震等級3の取得を検討する
耐震性の高いマイホームは、家族の命と財産を守るためにとても重要です。

「安さ」だけで選ぶのではなく、「長く安心して暮らせる家」かどうかを基準にして選びましょう。