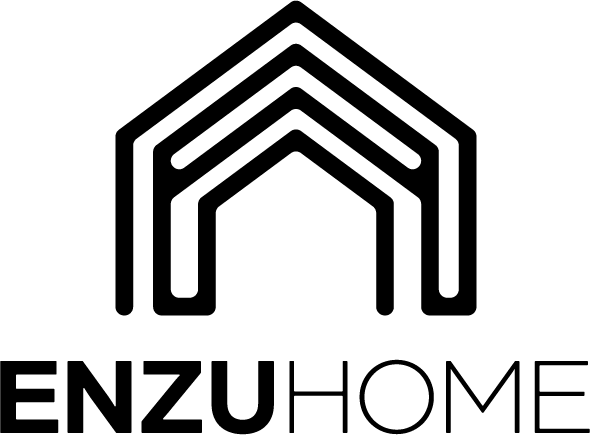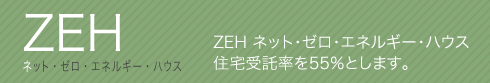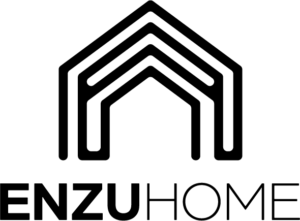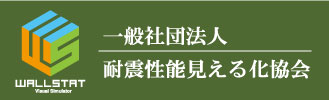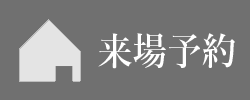相続登記の義務化で登記費用がかかる、、、
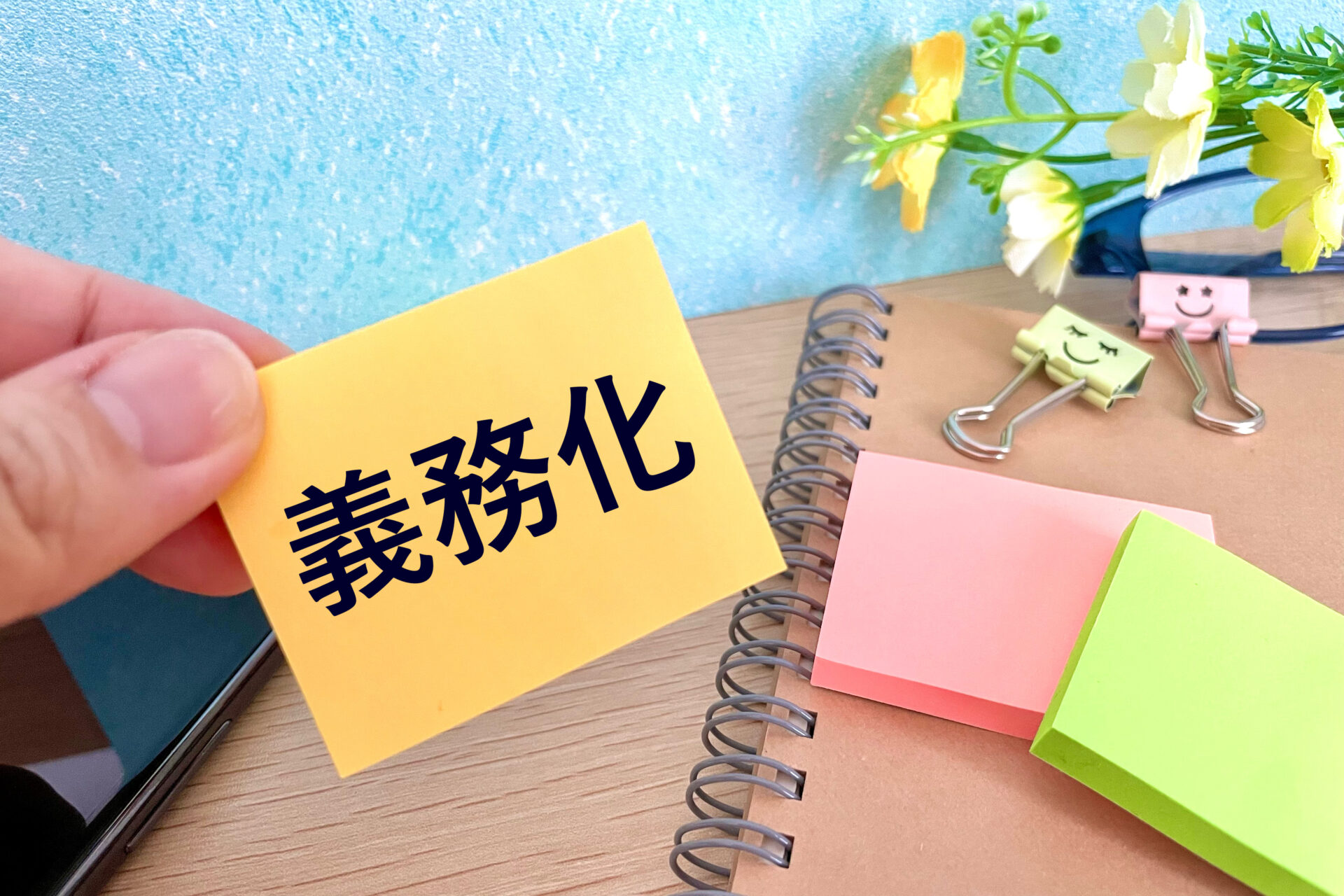
「親から土地を相続したけれど、そのままにしている……」そんな方はいませんか?これまでは義務ではなかった不動産の相続登記ですが、2024年4月から法律で“義務化”されました
この制度改正により、相続した不動産の登記を行わないと、最大10万円の過料(罰則)が科される可能性も。さらに登記を怠ると、売却や名義変更、他の相続人とのトラブルなど、思わぬ問題にも発展します。
本記事では、相続登記義務化の背景から、対象者・必要書類・手続きの流れ・罰則・よくある質問までをわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、自分に義務があるのか・今なにをすべきかがスッキリ理解できるはずです。将来のトラブルを避け、大切な資産を守るためにも、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ義務化されたのか
相続登記の義務化は、所有者不明土地の急増という深刻な社会課題に対応するために導入されました。現在、日本国内では相続されたまま登記されていない土地や建物が多数存在しており、その面積はなんと九州本島以上とも言われています。
所有者不明の不動産が増加すると、公共事業が進まない・災害時の復旧が遅れる・空き家問題が悪化するなど、社会インフラや地域の安全にも大きな影響を与えます。
こうした状況を受けて、政府は2024年4月に民法・不動産登記法を改正し、「相続で不動産を取得したら、3年以内に登記申請をしなければならない」という登記義務制度を導入しました。これにより、今後は相続発生時点で権利関係を明確にし、不動産の有効活用と権利トラブルの未然防止が期待されています。
義務化の対象者とは
相続登記義務化の対象となるのは、不動産を相続によって取得したすべての相続人です。たとえまだ名義変更をしていなくても、「相続で不動産を取得した事実を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。
これは単独で不動産を取得した場合はもちろんのこと、複数の相続人で共有する場合にも同様に適用されます。
特に注意すべきは、法定相続分のまま共有状態で放置されているケースです。このような状態でも登記義務は発生しており、一人でも義務を怠れば過料の対象となる可能性があります。相続人全員が登記の義務と期限を正しく理解し、協力して対応することが求められます。早めの準備が後々のトラブル回避に繋がります。
いつから施行されたのか
相続登記の義務化は、2024年4月1日に施行されました。これにより、すべての相続人に対して法的な登記義務が課されるようになりました。
この法律は施行日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生していた未登記の相続案件にも適用されます。特に注意が必要なのは、過去の相続で長年放置されていた不動産です。このような物件についても、2027年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
この「経過措置期間」が設けられている間に準備を進めれば、罰則を回避しつつ円滑な手続きが可能です。法改正を機に、自分や家族が関係する未登記の不動産がないか、今一度確認しておくことをおすすめします。
罰則規定について
相続登記を義務付ける新制度では、期限内に正当な理由なく登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この「過料」は刑罰ではなく行政上の制裁であり、前科が付くことはありませんが、公的義務に違反した記録として扱われます。「正当な理由」として認められるのは、戸籍の取得に時間がかかっている、相続人間で協議中など合理的な事情がある場合に限られます。
しかし、「忙しいから後回しにした」「よくわからないから手を付けていない」といった理由は正当と認められず、過料の対象となる可能性が高まります。登記の期限を意識し、早めに準備と手続きを開始することが、リスクを回避する最善策です。
過去の相続にも適用される?
はい、今回の相続登記の義務化は、過去に発生した相続にも遡って適用されます。
たとえば、10年前や20年前に発生した相続で、登記がされていない不動産があった場合でも、2027年3月31日までに登記を完了しなければなりません。この期限は、過去の未登記不動産に対して設けられた「経過措置期間」です。現在のうちから対応すれば、十分に間に合う期間が確保されています。
ただし、何代にもわたって登記が行われていない場合は、すべての相続人や関係戸籍をたどる必要があり、時間と労力がかかる可能性があります。早期に着手することで、手続きの負担を軽減し、将来の相続トラブルを未然に防ぐことができます。まずは不動産の登記状況を確認してみましょう。
所有者の権利保全
相続登記を行うことによって、自分がその不動産の正当な所有者であるという法的な証明ができます。
登記がされていない状態では、他の人に勝手に売却されたり、権利を主張されたりするリスクが残るため、非常に危険です。実際、登記されていないことで売却や担保設定ができないケースも多く、資産としての価値を十分に活かせなくなります。
義務化により、すべての不動産に正確な所有者情報が記録されることで、不正利用の防止や相続トラブルの抑止にもつながります。将来の相続人や家族に迷惑をかけないためにも、「登記による権利の保全」を意識して行動することが重要です。
不動産売却の円滑化
相続登記がされていない不動産は、法的な所有者が不明確な状態となっているため、売却や賃貸などの取引ができません。
不動産の名義が故人のままになっていると、買主側に所有権が移せず、契約自体が無効となる可能性もあります。こうした状態を回避するには、早めに登記を済ませておくことが不可欠です。登記が完了していれば、将来的な売却や担保利用もスムーズに進みます。
空き家や遊休地の活用が社会的にも求められている今、登記によって不動産を「使える状態」にすることは、個人だけでなく地域全体の利益にもつながります。相続登記の義務化は、単なる法律の改正にとどまらず、資産を未来へつなげる大切なステップともいえるでしょう。
相続人間のトラブル回避
相続登記が行われないまま放置されると、時間の経過とともに相続人の数が増え、権利関係が複雑化してしまいます。
例えば、親の不動産を兄弟で共有していた場合、次の世代では従兄弟やその配偶者までが関与するような状態になることもあります。このような状態になると、遺産分割協議がまとまらず、登記がさらに遅れるという悪循環に陥りやすくなります。
登記を義務化したことで、相続発生後の早い段階で権利関係を整理する動きが促進され、相続人間の争いを未然に防ぐ効果が期待されています。トラブルを防ぐには、登記を通じて不動産の名義を明確にし、法的な整理を早期に行うことが何より重要です。
公共事業への支障軽減
所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧の大きな障害となっており、実際に多くのインフラ整備が遅れています。
たとえば、道路拡張や堤防の補強工事では、土地所有者全員の同意が必要です。所有者が分からない土地では、手続きが止まってしまうのが現状です。国土交通省によれば、所有者不明土地による事業遅延は全国で数千件にも上ると言われており、その影響は非常に深刻です。
登記義務化により、土地の所有者情報が法務局で迅速に確認できるようになることで、公共事業の円滑化が期待されています。社会全体の利益を守るためにも、相続登記の早期実施は個人の責任として求められる時代となりました。
空き家・空き地対策としての効果
空き家や空き地の多くは、相続登記が行われておらず、管理されないまま放置されている状態にあります。
このような不動産は、防災・防犯・衛生・景観の悪化といった地域課題の温床になり、近隣住民への悪影響も深刻です。登記義務化によって、相続人の責任が明確化され、空き家や空き地を放置しづらい仕組みが整備されました。
これにより、不動産の売却・賃貸・利活用の促進が進み、地域活性化や防犯対策にもつながると期待されています。相続登記は個人の資産整理というだけでなく、地域社会全体の安全と価値維持のための大切なアクションでもあるのです。
不動産の売却・活用ができない
相続登記をしていない不動産は、法律上の所有者が確定していないため、売却・賃貸・担保設定などの取引が一切できません。
たとえ実質的に相続して住んでいたとしても、登記簿に名前が載っていなければ他人と変わらないと見なされます。この状態では、不動産の価値を活かすことができず、資産としての機能が停止してしまうのです。
さらに、買主にとってもリスクが高く、トラブルの原因となるため、相続登記が未了の物件は取引の対象にすらなりません。相続登記の義務化は、こうした機会損失やトラブルを防ぐための第一歩。資産活用を考えるなら、登記は避けて通れない手続きです。
相続人が増えると複雑化する
相続登記を行わずに長期間放置すると、次世代、さらにその次の世代へと相続が重なっていきます。
その結果、相続人の数が10人、20人と増えてしまい、遺産分割協議が困難になるケースが少なくありません。特に問題なのは、相続人同士が面識もなく、連絡先が不明な場合。このような状態では、全員の同意を取るだけでも数年単位の時間がかかることもあります。
また、ひとりでも協議に応じない人がいれば、登記手続きはストップし、最終的には裁判所での調停・審判が必要となることもあります。義務化された今、早期の登記が相続人全体の負担を軽減し、スムーズな資産承継を実現する鍵になります。
固定資産税などの負担が続く
登記をしていない不動産であっても、固定資産税や都市計画税の納税義務は免れません。
名義が故人のままでも、実際に使用・相続している相続人に納付書が届くことがほとんどです。もし納税を怠った場合、延滞金や差押えといった法的措置が取られる可能性があります。登記を放置していることで名義変更もできず、所有者としての権利も責任も中途半端なままになってしまいます。
義務化を機に、権利と義務を明確化し、適切な管理責任を果たすことが、家族全体の安心と地域への貢献につながります。
罰則(過料)の対象となる
相続登記が義務化されたことで、正当な理由なく登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この過料は行政上の制裁であり、刑罰ではありませんが、法令違反として正式に記録されるため注意が必要です。「正当な理由」として認められるのは、相続人の調査に時間がかかっている、遺産分割協議中であるなど、やむを得ない事情がある場合に限られます。
一方で、「忙しかった」「手続きが面倒だった」という理由では過料の免除はされません。義務の履行を軽視せず、早めに行動を起こすことが自分と家族を守る第一歩になります。迷ったらまずは専門家や法務局に相談を。
トラブルや訴訟に発展する可能性
登記を行わないまま放置された不動産は、相続人間のトラブルの火種となる可能性があります。
たとえば、一部の相続人が勝手に土地を利用したり、無断で売却を試みたりするケースもあり、他の相続人との対立に発展します。また、登記がされていないと、第三者に対して自分の権利を主張できないという法的な弱点もあります。
最悪の場合は、訴訟に発展し、長期にわたる裁判費用や精神的な負担を抱えることにもなりかねません。登記を正しく行うことで、こうしたリスクを根本から回避し、安心して不動産を活用・管理することが可能になります。
登記申請に必要な書類とは
相続登記を行うには、複数の重要な書類を用意する必要があります。提出書類に不備があると、申請が受理されず手続きが遅れてしまいます。
基本的に必要とされるのは以下の通りです。
・相続人全員の戸籍謄本と住民票
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・遺産分割協議書(協議がある場合)
・不動産の固定資産評価証明書
・登記申請書および登記原因証明情報
相続人が多い場合や不動産が複数にまたがる場合は、必要書類の数も増えるので、早めにリストアップして準備することが大切です。
また、法務局や司法書士のウェブサイトでは、ひな形(記入例)も公開されているので、活用しながら記入ミスを防ぎましょう。万が一、どの書類が必要か不安な場合は、最寄りの法務局で事前相談を受けると安心です。
相続登記の基本的な流れ
相続登記の手続きには、いくつかの明確なステップがあります。流れを把握しておくことで、無駄な手戻りやトラブルを防ぐことができます。
一般的な流れは以下の通りです。
② 遺産分割協議:相続人全員で不動産の分け方を話し合い、合意します。
③ 必要書類の収集:戸籍、住民票、評価証明書などを揃えます。
④ 登記申請書の作成:法務局提出用の書類を作成します。
⑤ 法務局への提出:必要書類を添えて申請すれば完了です。
登記完了までには数週間〜1か月程度かかることもあるため、余裕をもって準備を始めることが重要です。
また、相続人が複数いる場合は、全員の署名・押印が必要なため、早めに連絡体制を整えておくことがスムーズな登記のカギになります。各手続きに不安がある場合は、司法書士など専門家に相談することで確実に進められます。
専門家に依頼する場合の費用感
相続登記の手続きはご自身で行うことも可能ですが、専門家(司法書士)に依頼することでスムーズかつ確実に進めることができます。
一般的な報酬の相場は、5万円〜15万円程度。不動産の数、相続人の人数、遺産分割協議の有無などにより、費用は上下します。このほかにかかるのが登録免許税で、これは不動産の固定資産評価額の0.4%と定められています。
司法書士によっては、初回相談が無料だったり、見積もりを事前に提示してくれる事務所も多いため、複数の事務所に相談して比較するのがおすすめです。手続きの安心感を重視するなら、専門家のサポートは非常に心強い選択肢といえるでしょう。
相続人申告登記とは
「相続人申告登記」とは、遺産分割がまだ済んでいない場合でも、とりあえず登記義務を果たすための制度です。
通常の相続登記では、不動産の名義変更まで完了させる必要がありますが、この申告登記では「私は相続人です」と申告するだけでよく、比較的簡易な手続きで済みます。必要書類は、申告書と相続関係を示す戸籍の写しなどのみ。遺産分割協議が整っていなくても提出できます。
この制度を利用すれば、とりあえず過料のリスクを回避できるため、時間がかかる相続案件の「つなぎ」として非常に有効です。ただし、これはあくまで最終的な登記手続きの猶予であり、後日あらためて名義変更登記を行う必要がある点には注意が必要です。
期限までに準備すべきこと
相続登記の義務には明確な期限が定められています。
相続で不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に登記申請を完了させなければなりません。また、過去に発生していた相続で登記されていない不動産については、2027年3月31日までに申請することが義務となっています。
そのため、今のうちにできる準備としては以下のようなものがあります:
・家族で相続対象の不動産を洗い出す
・被相続人および相続人の戸籍や住民票を収集
・遺産分割協議が必要な場合は、早めに話し合いを開始
手続きには時間がかかるケースもあるため、思い立った「今」が一番早いと考えて、計画的に動き出すことが重要です。もし手続きの全体像が不安な場合は、法務局や司法書士への相談を活用して、安心して進めましょう。
過去の相続も義務の対象ですか?
はい、今回の登記義務化は過去に発生した相続にも遡って適用されます。
たとえば、2000年に親を相続したが登記していなかったという場合でも、義務を果たす必要があります。
このような過去の未登記不動産に関しては、2027年3月31日までの猶予期間(経過措置)が設けられています。この期間内に登記を行えば過料の対象とはなりませんが、期限を過ぎた場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
対象となる不動産がないか、家族や親族で早めに確認し、必要があればすぐに準備を始めることが大切です。
相続人が多数いる場合はどうすれば?
相続人が多い場合でも、登記には全員の同意が必要です。
1人でも協議に参加できない、または同意しない相続人がいると登記手続きが進まなくなります。具体的には、遺産分割協議書を全員で作成し、署名・実印の押印と印鑑証明書の添付が求められます。
相続人が全国各地に散らばっている場合や、連絡がつかない場合には、司法書士などの専門家に相談して段取りを整えるのが現実的です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判によって手続きを進めるという方法もあります。
人数が多いほど手間と時間がかかるため、相続発生後はできるだけ早めに関係者と連絡を取り合い、準備を進めることが重要です。
登記をしないとすぐに罰則がありますか?
登記義務に違反したからといって、すぐに罰則(過料)が科されるわけではありません。
罰則が適用されるのは、正当な理由もなく登記を怠り続けた場合に限られます。たとえば、戸籍の取得に時間がかかっている、相続人間で協議中などは正当な理由として認められる可能性があります。
しかし、「手続きが面倒だった」「知らなかった」という理由では、過料免除の対象とはならない点に注意が必要です。少しでも不安がある場合は、早めに法務局や専門家に相談し、事情を記録に残しておくことがリスク回避につながります。
司法書士に頼まないとできませんか?
相続登記は本人でも手続き可能です。
必ずしも司法書士などの専門家に依頼する必要はありません。法務局のホームページでは、登記申請書のひな形や必要書類の案内が公開されており、窓口での相談も無料で受け付けています。ただし、戸籍の読み取りや書類作成に不安がある場合や、相続人が多い・不動産が複数あるケースでは、司法書士に依頼することで確実に手続きを進めることができます。
専門家に頼めば、書類の不備や提出ミスによる手戻りも防げるため、時間と手間を大きく軽減することが可能です。コストは発生しますが、安心を優先したい方には非常に有効な選択肢といえるでしょう。
そもそもどこに相談すればいい?
相続登記についての相談は、法務局や司法書士などの専門機関が窓口となります。
全国の法務局では、相続登記に関する無料相談を実施しており、予約をすれば具体的な手続き内容や必要書類の確認が可能です。また、地域の司法書士会でも定期的な無料相談会を開催しているため、専門家のアドバイスを直接受けられる良い機会となります。
相続人間でトラブルが発生している、協議がまとまらないといった場合には、弁護士への相談も選択肢の一つです。まずは自分でできる範囲の情報収集を行い、「わからないことが出てきたら迷わず相談」という姿勢が、スムーズな登記手続きのカギになります。
まとめ
2024年4月に施行された相続登記の義務化は、これまで曖昧になっていた不動産の所有権を明確にし、トラブルや社会的なコストを削減するための重要な制度改正です。
登記の義務は相続発生から3年以内、過去の未登記分は2027年3月31日までと期限が明確に定められています。登記を怠ることで生じるリスクは、過料・資産の凍結・相続人間の対立・固定資産税の負担など多岐にわたり、大切な家族や将来の相続にも悪影響を及ぼします。
一方で、登記を行うことで不動産の権利が保全され、資産の活用や売却、地域の活性化にもつながるという大きなメリットがあります。手続きに不安がある方は、法務局・司法書士・弁護士などの専門家に相談することで安心して進められます。「わからないままにしない」ことが、将来の備えになります。
✅ 相続登記義務化の概要
対象:相続により不動産(土地・建物)を取得した相続人。
期限:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
罰則:正当な理由なく期限内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続・遺言に関する無料相談はあいりん司法書士事務所
📌 注意点と対策
1. 過去の相続も対象
2024年4月1日以前に発生した相続で、未登記の不動産も義務化の対象となります。この場合、2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。
2. 登記を怠るリスク
不動産の売却や担保設定ができない。
相続人が増えることで、権利関係が複雑化し、手続きが困難になる。
固定資産税などの費用負担が継続する。
3. 登記が難しい場合の対応
遺産分割協議がまとまらないなど、すぐに登記ができない場合は、「相続人申告登記」を行うことで、義務違反を回避できます。
📝 登記手続きの流れと必要書類
手続きの流れ
相続人の確定(戸籍の収集)
遺産分割協議の実施(必要に応じて)
登記申請書の作成
法務局への申請
必要書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人の住民票
遺産分割協議書(協議がある場合)
不動産の登記事項証明書
固定資産評価証明書
詳細は法務省のQ&Aをご参照ください。
法務省
💰 登記にかかる費用
登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%。
司法書士報酬:依頼する場合、5万円〜15万円程度が一般的です。