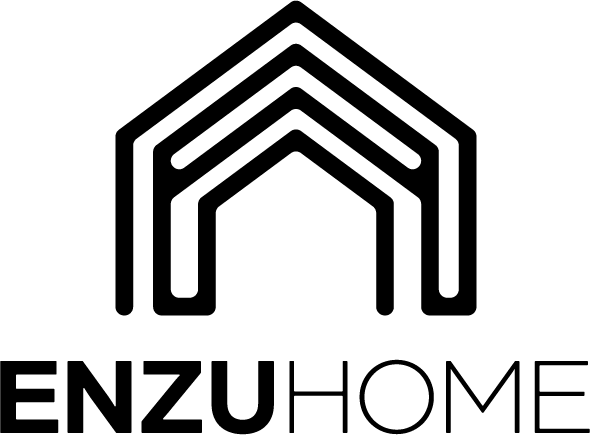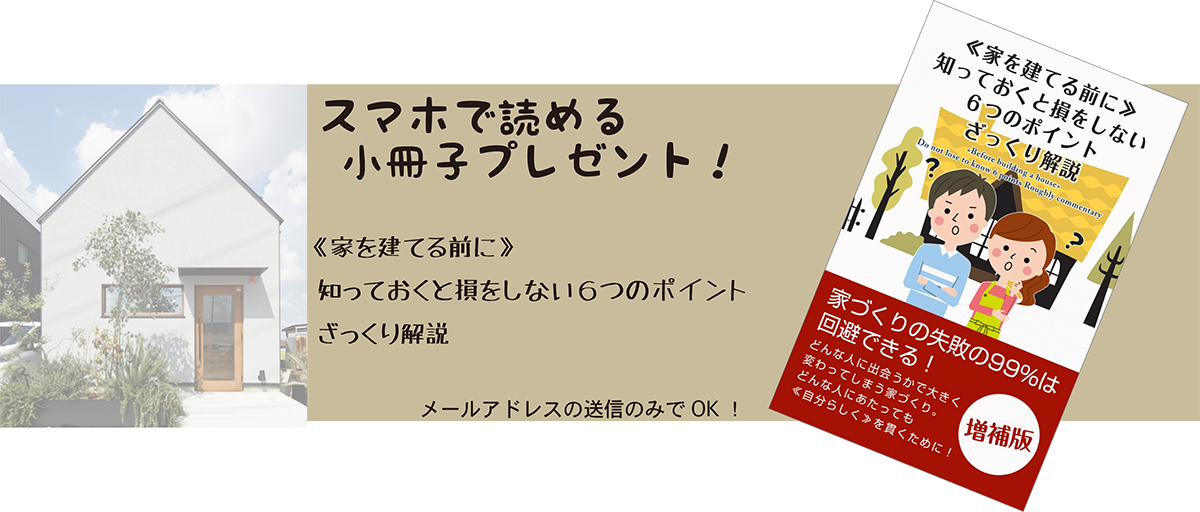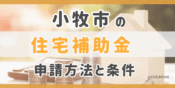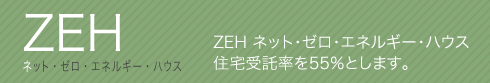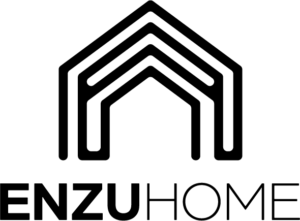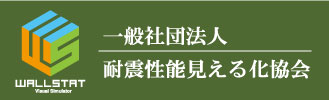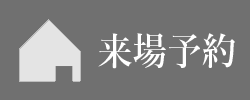筋交いの基本がわかる! 重要ポイント5選も解説

- 筋交いって結局なに?必要なの?
- 耐力壁との違いがよくわからない
- 地震対策として本当に効果あるの?
地震に強い家づくりを考える上で、「筋交い」や「耐力壁」という言葉をよく聞くものの、具体的な役割や重要性がわからず、不安を感じていませんか?

そこで、二級建築士のオガタが筋交いについてわかりやすく徹底解説し、あなたの疑問をスッキリ解消します。
- 筋交いの役割と種類
- 耐力壁との違いや設置時の注意点
- 実際によくある疑問とその答え
特に、耐震性能を重視したいあなたは、ぜひ最後までご覧ください。
筋交いの重要性3つを解説

木造住宅においては、柱と柱の間に斜めに入れられるこの補強材が、建物の安定性を大きく左右します。

なぜ筋交いが住宅の構造においてそれほど重要なのか、その3つのポイントに分けてわかりやすく解説します。
重要性①:地震や台風など横からの力に耐える
地震対策。家を建てる時にはその土地が農地や沼地の埋め立て地(盛土地)でないか確認しましょう。建売住宅では費用がかかる基礎に手を抜いているので、数年で傾きます。また筋交い、火打ちも省くので地震に弱い。以前建売の工事現場でなぜ火打ちを入れないのか?と尋ねたらベニアで押さえるから大丈夫
— りゅうは (@ryuuha777) February 2, 2025
筋交いは、地震や台風などによって建物にかかる「横からの力(水平力)」に対抗するために不可欠な構造材です。

特に日本のように自然災害が多い国では、建物の揺れを抑えるために筋交いの存在は非常に重要です。
この部材を適切に配置することで、建物全体の剛性(かたさ)を確保することができます。
- 地震による横揺れ
- 台風による強風
- 家屋のねじれ防止
重要性②:建物の変形や倒壊を防ぐ
強風にあおられ 金沢の工事現場で高さ8メートルの足場が倒壊 けが人なし
— xxx😄🥃🍾 (@will_help17785) April 8, 2025
何 この足場の組み方 まるで素人の足場の組み方じやない。筋交い1本も入ってないし、強度不足もいい所。建設現場なら通用しない足場の組み方 https://t.co/jydnooFS7w
筋交いは、柱と柱の間に斜めに取り付けることで、長方形のフレームをひし形に変形させないようにする役割があります。

これにより、建物がゆがんだり傾いたりするのを防ぐことができ、倒壊リスクの大幅な軽減につながります。
- 構造の安定化
- 建物の長寿命化
- 家族の命と財産を守る安心感
重要性③:耐震基準を満たすために必要不可欠
聞き流してたらビビったわw
— Cheese tart 08 (@Cheesetart08) January 23, 2024
…ともかく再現したのすげーな pic.twitter.com/j8naKStfkN
筋交いは、建築基準法において耐力壁としての役割が定められており、新築住宅には必ず設置が必要です。
また、既存住宅の耐震リフォームを行う際も、筋交いを適切に追加・補強することで耐震等級の向上が期待できます。

国が定めた安全基準をクリアするためにも、筋交いの存在は欠かせません。
【耐震基準との関係】
| 耐震等級 | 説明 |
|---|---|
| 等級1 | 建築基準法に定められた最低限の耐震性を満たす水準 |
| 等級2 | 等級1の1.25倍の強さ。学校・病院などに推奨 |
| 等級3 | 等級1の1.5倍の強さ。消防署・警察署レベルの耐震性 |
筋交いを正しく配置し補強することで、これらの等級に対応した家づくりが可能になります。
関連記事:【知らないと後悔】「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違いやデメリット5つを解説!
筋交いの基本3つを解説

筋交いは、建物の強度や耐震性を高めるうえで、最も基本的な構造部材のひとつです。

ここでは、筋交いの定義や種類、そして法律との関係について、基本ポイントを3つに分けて解説します。
基本①:建物を強くするために柱の間にななめに取り付ける補強材
新耐震基準(1981年)以降の建物だから安心。
— Konstnar (@konstnar2011) January 2, 2024
というのは正しくない。
こちらは新耐震以降の1989年に確認を受けた木造2階建て住宅。
耐力壁(筋交い)の数が確認申請上の図面の耐力壁の数より5本少なかった。
更にその数少ない筋交いにも換気扇やエアコン配管が貫通していた。… pic.twitter.com/akEcQN6WYV
筋交いとは、柱と柱の間に斜めに取り付けられる部材のことです。
地震や強風といった横からの力に抵抗し、構造の「ねじれ」や「ゆがみ」を防ぎます。

筋交いがあることで、四角形の枠がひし形に変形するのを抑え、建物の倒壊を防ぐ役割を果たします。
基本②:片筋交いとたすき掛けの2種類がある
木造の建物の柱と柱の間には「筋交い」という斜めの部材があります。風や地震など横方向の力に抵抗する役割です。
— ふる (@163198_dsk12) August 1, 2021
筋交いは向きや入れ方、固定の仕方が決まっています。また、建築基準法でも筋交いの規定がいくつかあります。 pic.twitter.com/svYEmiAfSr
筋交いには主に2つのタイプがあり、それぞれ耐震性や施工コストに違いがあります。

リフォームや新築の際には、建物の構造や予算に応じて適切なタイプを選ぶことが大切です。
片筋交い(かたすじかい)

柱と柱の間に、斜め1本だけの補強材を入れるタイプです。
シンプルな構造であり、コストが抑えやすく施工も比較的簡単な点がメリットです。
ただし、1方向からの力に対しては強いものの、反対方向からの力には弱いという特性があります。

そのため、片筋交いを使う場合は、全体のバランスを考慮して左右対称に配置するなどの工夫が求められます。
たすき掛け(クロス筋交い)

柱と柱の間に、「×」の形で2本の筋交いを交差させて取り付けるタイプです。
片筋交いの約2倍の耐力(=壁倍率)があり、より強度が求められる場所に最適です。
ただし、材料費や施工手間が増えるため、コストは高めになります。

住宅の中でも、耐力が特に必要な壁や、地震に強くしたい箇所に使用されることが多いです。
基本③:建築基準法で厚みや幅、金物の使用が定められている
ここで「木造戸建なら00年代~の物を買おう」と書いたワケは、
— 実家ホ~ムのホムイさん (@HomelessArai) April 27, 2024
「2000年6月(たしか)の建築基準法改正で、筋交いの接合方法等、『やっと木造がマトモな耐震基準をもった』から」なのだ🫵(´・ω・`)
1枚目はそれまでの「釘うっただけの筋交い」だそーなのだ。これだと地震ですっぽ抜けてグシャアー。 https://t.co/IE4g6eY2qy pic.twitter.com/ZYIXuFfphz
筋交いは建築基準法により、材質・厚み・幅などが明確に規定されています。
また、柱や梁と緊結する際には、必ず金物(ボルトや筋交いプレートなど)を使用することが義務付けられています。
【筋交いの法的基準の一例】
| 種類 | 厚さ | 幅 | 接合部の条件 |
|---|---|---|---|
| 引張力用 | 1.5cm以上 | 9cm以上 | 金物で柱・梁と緊結 |
| 圧縮力用 | 3cm以上 | 9cm以上 | 欠き込みなし、または補強を実施 |
正しく施工されていない筋交いは、地震の際にその効果を発揮できない恐れがあります。
そのため、筋交いの設置には法令順守と専門知識が欠かせません。

これらの基本を押さえておくことで、安心・安全な住まいづくりの第一歩となります。
筋交いの役割3つ

筋交い(すじかい)は、住宅の構造を強化するうえで欠かせない存在です。
特に耐震性に直結するパーツとして、現代の木造住宅では必須ともいえる役割を担っています。

ここでは、筋交いが果たす3つの大切な役割を解説します。
役割①:横方向の揺れに対する耐力を高める
4号機まずいな。東電HPにある写真だけど、筋交いの役割をする壁を撤去している。このタイミングで地震が来たら、横方向の力には耐えられない。(画像) pic.twitter.com/JWdtrFxW
— cmk2wl (@cmk2wl) January 2, 2012
筋交いは、柱と柱の間に斜めに入れることで、建物が揺れたときの“ねじれ”や“ひし形変形”を防ぐ補強材です。
地震や台風など、横方向からの強い力に対して構造をしっかり支えます。

特に以下のような揺れに対して、筋交いが効果的です。
- 地震による横揺れ
- 台風などの強風による振動
- 建物の揺れ戻しによる負荷
筋交いがあることで、住宅の耐震性は大きく向上します。
役割②:建物全体の構造バランスを安定させる
これは昨年訪れた屋久島町役場の庁舎内部。
— 阿久津健一 (@ak2ken1) May 29, 2020
昨年の5月に竣工したばかりという事もあり屋久杉を使って立てられた庁舎は良い香りに包まれていました。
主柱から放射状に伸びる筋交いと梁と柱の役割を持たせた様な斜めの部材が大地から生える屋久杉の姿を表現してると思われ素敵なデザインでした。 pic.twitter.com/JeUa0reB4U
筋交いは、バランス良く配置することで建物全体の安定性を高めます。
逆に、一方向だけに集中して配置されると、地震の揺れに対して偏った動きが生じ、構造的に不安定になることもあります。

構造計算や建築士の判断に基づき、以下の点に注意して配置されます。
- 張り間方向とけた行方向の両方にバランスよく設置
- 上下階でできるだけ同じ位置に配置
- 耐力壁の総量と配置バランスの最適化
このような配置により、建物の“ねじれ”や“局所的な弱点”を防ぐことができます。
役割③:耐震等級を上げるための補強要素となる
耐震等級3でお願いしたので、棟梁に「耐力壁使いながら、これだけ筋交い入れるの珍しいですよ」と言われた。 pic.twitter.com/7auG81ZRLS
— むしまる(本家) (@fudesakisanzun) March 8, 2020
耐震等級は、建物の地震に対する強さを示す指標で、住宅ローン減税や補助金制度の条件にもなります。
筋交いは「耐力壁」の一部として評価され、等級を上げるための重要な構造要素です。
- 筋交いを増やすことで壁倍率が上がる
- 壁倍率が一定以上になると、耐震等級2~3の基準を満たす
- 高い耐震等級により、住宅の安全性や資産価値も向上

このように、筋交いは建物の安全性だけでなく、将来的な資産保護にもつながる大切なポイントです。
関連記事:高気密高断熱の住宅はなぜ気持ち悪いと言われる?10個の理由と対策を不動産のプロが徹底解説!
耐力壁の筋交いの注意点3つ

住宅の耐震性を高めるうえで欠かせない「筋交い」。
しかし、入れ方や設置場所を間違えると、期待していた効果を十分に発揮できません。

ここでは、筋交いに関する重要な注意点を3つに絞って解説します。
注意点①:向きや配置のバランスによって耐震性が変わる
老後も快適に住うためのひとつの方法として、間取りは改装すること前提で設計することがあげられます。
— Bさん@アーキトリック (@architrick_net) June 30, 2020
具体的には
・間仕切り壁に筋交い(耐力壁)を設けない
・玄関からの廊下は直線でかつ広めにする
・リビングダイニングの近くに部屋を設ける
特に筋交い位置は設計段階から注意しましょう。
筋交いはただ入れればいいわけではなく、「どこに・どの向きで」入れるかが非常に重要です。
建物の左右・前後でバランスよく配置されていないと、地震時に建物がねじれてしまい、倒壊のリスクが高まります。
【配置バランスの基本ポイント】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 向きのバランス | ハの字と逆ハの字を交互に配置 |
| 上下階の位置 | 同じ位置に配置することで力の伝達がスムーズ |
| 全体バランス | 左右・前後で均等に配置するのが理想 |

筋交いの本数ではなく、バランスを意識することで、耐震性の高い構造になります。
注意点②:法律に基づいた金物の使用と正確な施工が必要

筋交いの設置には、建築基準法により厚みや幅、取り付け方法が細かく定められています。
特に接合部分には、ボルトやプレートといった専用の金物を使用しなければなりません。
【建築基準法における筋交いの仕様】
| 種類 | 必要な仕様 |
|---|---|
| 引張り筋交い | 厚さ1.5cm以上 × 幅9cm以上 |
| 圧縮筋交い | 厚さ3cm以上 × 幅9cm以上 |
| 接合方法 | 金物(ボルト・プレート等)で柱や梁に緊結 |
| 欠込み加工 | 原則NG(たすき掛けの場合は補強すれば可) |

正確な施工が行われていないと、筋交い本来の効果が発揮されず、耐震性が著しく下がってしまいます。
注意点③:筋交いの本数よりも全体の構造バランスが重要
耐震補強工事の現場も順調に進んでいます。
— 中川義仁 棟梁 枚方の中川忠工務店 (@Nakatyuu1203) May 9, 2019
土壁を撤去し、地震による強い揺れに備えて筋交いを入れています。
筋交いを入れることで、建物に加わる横の力に抵抗。
建物の構造を安定させます。
筋交いは、耐震診断の結果を元にバランスよく配置させることが大切!#家づくり #大工 #耐震補強 pic.twitter.com/YoicYyrRz1
「とにかく多く入れれば安心」と思われがちですが、それは大きな誤解です。
筋交いを増やすだけでは、耐震性能は上がりません。
むしろ、過剰な設置や偏った配置は建物の変形を招くリスクがあります。
【よくある誤解と正しい考え方】
| 誤解 | 実際のポイント |
|---|---|
| 筋交いは多いほど良い | 数よりも配置のバランスが重要 |
| 壁の強化だけで耐震性UP | 建物全体の設計・構造が関係する |
| 各部屋で補強すれば安心 | 上下階での位置合わせも必要 |
バランス良く設計された構造が、真の耐震性を生み出します。
筋交いの配置には専門的な知識が求められるため、設計段階から建築士や構造計算のプロに相談することが大切です。
筋交いは住宅の命綱とも言える構造部材。

正しい理解と施工で、安心して暮らせる住まいをつくりましょう。
筋交いに関する質問5選

ここでは、実際によく寄せられる「筋交いに関する5つの質問」に対して、専門的な視点からわかりやすく解説していきます。

家づくりや耐震リフォームを考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
質問① 筋交いの代わりになるものはある?
筋交いの代わりに火打金物で補強して、だんだん家っぽくなってきた!#日曜大工 #大工 #DIY #リフォーム pic.twitter.com/314QUEOBAh
— キィ (@Q78STdRh6xejwRc) July 8, 2018
筋交いの代替手段として、以下のような構造補強方法があります。
- 構造用合板などの耐力面材を使った壁補強
- 金属ブレース(鋼製の斜材)
- 制震ダンパー(揺れを吸収する装置)
中でも面材耐力壁は、筋交いと違い面全体で地震の力を受け止めるため、より安定した補強が可能です。

近年では、制震技術との併用も増えています。
質問② 耐力壁と筋交いはどっちが必要?

どちらも住宅の耐震性を高めるために重要な要素です。
それぞれの違いを表で確認しましょう。
| 項目 | 筋交い | 面材耐力壁 |
|---|---|---|
| 材料 | 木材や金属などの斜材 | 構造用合板などの面材 |
| 耐震性 | 中程度(たすき掛けで強度UP) | 高い(面全体で揺れに対応) |
| メリット | 軽量でコストが安い | 工期が短く、断熱との相性が良い |
| デメリット | 向きや本数に注意が必要 | 費用がやや高くなることもある |

筋交いは在来工法に多く用いられ、面材はツーバイフォー工法に多く採用されています。
質問③ 筋交いを入れる場所はどこ?
セルフビルド。耐震補強の筋交い入れ。助っ人ふたりの活躍で予定の場所全てに筋交いが入りました。続いてはこれの上下両端を金物で留めていきます。金物は専用のものが売られてます。耐震の要になるからか、ネジの数が半端ないです。親父が田舎から助っ人に来てくれたので、頑張ってもらいました。 pic.twitter.com/Lz5bfyvpUz
— 阪口 克 (@katumi_sakaguti) February 15, 2019
基本的に、柱と柱の間に斜めに設置します。
- 建物の四隅や中央など、バランスよく配置する
- 1階と2階で壁の位置を揃えると耐震性がアップ
- 偏った配置や一方向だけの設置はNG

耐震診断や設計段階で、構造バランスに配慮した配置が必要です。
質問④ 筋交いの壁倍率は?
各会社で使用している面材耐力壁や筋交いから
— 早川浩平/いつまでも変わらない日常を (@ez_structure) September 30, 2023
許容応力度計算による耐震等級3を取得するのに
どれくらい壁の枚数が必要なのかを見える化しておくと
意匠設計時に検討をつけやすいですね
そしてこうやって見ればそんなに壁の枚数必要ないし
壁倍率5倍以上を使わなくてもだいたい確保できます pic.twitter.com/uFS1HPOeSW
筋交いは取り付け方によって耐震性(壁倍率)が変わります。
| 筋交いのタイプ | 壁倍率の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 片筋交い(1本) | 1.0倍 | 最も基本的な補強方法 |
| たすき掛け(2本交差) | 2.0倍 | 片筋交いの約2倍の強度 |
| 金属ブレース | 1.5〜2.5倍 | 鋼材を使い耐震性をさらに向上 |

建物の構造や設計条件によって、最適なタイプを選びましょう。
質問⑤ 筋交いの耐震効果はある?
【耐震・制震・免震】
— 永野数学塾 永野裕之 (@naganomath) February 10, 2012
・耐震:建物を強くする(筋交いを入れる等)
・制震:揺れを弱める(天上から振り子を吊るして振れを打ち消し合う等)
・免震:揺れが建物に伝わりづらくする(建物を浮かしたり、ゴムや金属球で揺れを吸収する等)⇒耐震、制震、免震の3つを組み合わせると大きな効果。
筋交いは地震による横揺れから建物を守るために非常に重要です。
- 建物の変形を防止して倒壊リスクを軽減する
- 応力を壁全体に分散し、バランスの良い強度を確保
- 耐震等級アップにもつながる補強手段
ただし、正しい設置や金物の使用が前提となります。

施工の質次第で効果は大きく変わります。
信頼できる業者に依頼しましょう。
関連記事:愛知県で家を建てるならどこ?おすすめエリア10選を徹底解説!
まとめ:筋交いは耐震性を支える住宅の要

- 建物の耐震性を高めるために不可欠な筋交いの設置
- 筋交いの種類や施工法を理解した上での正確な補強
- 耐震性と構造バランスを両立するリフォーム計画の重要性
筋交いは、地震や台風など横からの力に耐えるために欠かせない構造部材です。

正しい位置と方法で取り付けることで、住宅全体の耐震性が大きく向上します。
安心して長く住み続けるためにも、筋交いを含めた耐震補強の知識を持ち、信頼できる専門業者に相談することが大切です。